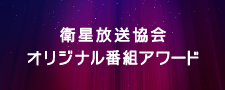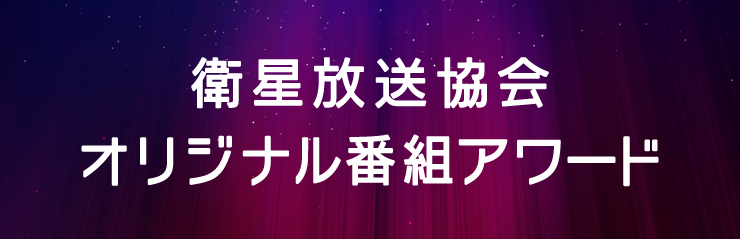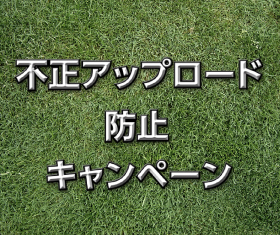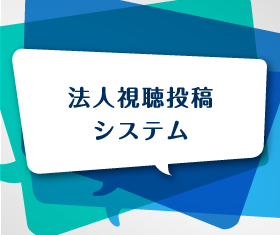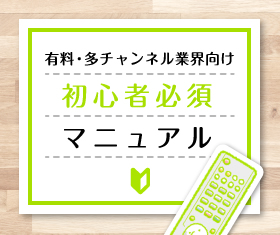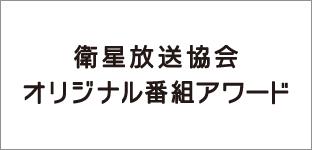活動報告
2019年
青少年健全育成活動「テレビ番組のイベント現場を親子で体験しよう!」
「B.LEAGUE 川崎ブレイブサンダース 対 琉球ゴールデンキングス」
2019.12.25
衛星放送協会の倫理委員会では、青少年健全育成活動として、新小学4年生~新中学3生とその保護者を対象に 『テレビ番組のイベント現場を親子で体験しよう!』を毎年開催しています。
今年は、日本の男子プロバスケットボールのトップリーグであるB.LEAGUE、川崎ブレイブサンダースのご協力を得て、ホームスタジアムの川崎市とどろきアリーナで12月8日(日)に開催しました。

次に子供たちは、試合の生中継を制作する(株)スカパー・ブロードキャスティングに協力頂き、会場内に設営された放送席と、屋外にある中継車の内部に入って見学し、生中継の仕組み、放送に携わる方々の役割、機材の説明を受け、熱心に聞き入りました。そしていよいよ、5人の子供たちは制作体験をするために、中継車班と放送席班で担当を決めました。中継車班の2人は、まず全体を演出し全スタッフに指示を出すディレクター、カメラ映像を切り替えるスイッチャ―、放送席班の3人は解説者、アナウンサー、そして中継車ディレクターから出された指示をアナウンアーに伝えるフロアディレクターの担当に分かれて、番組オープニング部分の制作体験をしました。2度のリハーサルで子供たちはすぐにコツをつかみ、本番ではそれぞれが役割を見事にこなし、プロ顔負けの素晴らしい出来栄えとなりました。


最後に子供たちは試合開始前の選手入場時に、選手とのハイタッチにも加わって頂き、喜んで頂きました。 プロスポーツの運営や、テレビの生中継には大勢の関係者が関わり、チームワークで成り立っていることを学んでいただきました。同伴された保護者の皆様からは「子どもと将来の仕事について話しあう話題作りができました」、「試合を支える側の仕事経験は貴重な機会でした」と、好意的な感想を頂戴しました。

衛星放送協会では、青少年が将来に向け大きな夢を持ち、職業人となる自覚を高めてもらうことを願い、今後も青少年健全育成活動を実施して参ります。
| 開催日時 | 2019年12月8日(日)13:00~16:00 |
|---|---|
| 会場 | 川崎市とどろきアリーナ(神奈川県川崎市) |
| 内容 | 男子プロバスケットボール B.LEAGUE 川崎ブレイブサンダース対琉球ゴールデンキングスの会場で、来場者の受付体験と、番組の生中継設備見学および番組制作の体験 |
| 参加者 | 小学生と保護者 5組 |
第14回人材育成セミナー
2019.12.23
総務委員会では、2019年10月に「第14回人材育成セミナー」を開催いたしました。今回は、業界の働き方改革への取り組みの一環として「子育てと仕事」をテーマに、都内に認可保育所「まちの保育園」認定こども園「まちのこども園」を運営し、地域と保育をつなぐ〝まちぐるみの保育〟を実践している「ナチュラルスマイルジャパン株式会社」「まちの研究所株式会社」代表 松本理寿輝氏を迎え、参加者との対話を交えながら多様化する社会におけるこれからの子育てと業界について考えました。

松本理寿輝氏
セミナーは2部構成で行われ、第1部では「まちぐるみ 会社ぐるみの保育とは?~これからの子育てで知っておきたいこと」と題し、松本氏が保育の現場から得られた知見をもとに、子どもの意思を尊重し感性を活かす教育保育について語られました。
第2部では、「すくすく子育て 衛星放送協会版! 子育ての疑問・悩み相談会」として、参加者への事前アンケート調査で浮き彫りになった課題「子育て家庭が持つ悩み」「子育て家庭の働き方」について、松本氏を交えた参加者によるディスカッションが行われました。ディスカッションは予定時間を30分オーバーし、子育て家庭が抱える問題の切実さが伺えるセミナーとなりました。
また、セミナー内容と詳細は、働きやすい職場作りへの参考としていただくことを目的に、後日レポートとして衛星放送協会の正会員各社に配布されました。

| 開催日時 | 2019年10月18日(金) |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 参加社数 | 10社 18名 |
第6回スポGOMI大会
2019.11.28

衛星放送協会では、会員社自ら社会貢献に参加する「スポGOMI大会」を2014年から毎年実施しています。
今年は、10月26日(土)東京・赤坂で「第6回スポGOMI大会」を開催しました。同大会は、日本スポGOMI連盟が全国展開しているルールに沿って、5人前後でチームを作り60分間で収集したゴミの種類と重量をポイント化して順位を競うもので、ゴミ拾いに競技感覚を取り入れた社会奉仕活動です。
当日は爽やかな秋空のもと、衛星放送協会の会員21社113人が19チームに分かれて、東京都港区立氷川公園を拠点に赤坂一帯を清掃しました。赤坂の繁華街も場所によってはクリーンで、参加者からは「ゴミが落ちていない」と嬉しい悲鳴が聞こえてきた一方で、前日に関東一帯を通過した台風21号の影響で、壊れたビニール傘が例年以上に回収されました。

スポGOMI大会のルールは、缶や瓶よりも、ペットボトルやタバコの吸い殻がポイント高く、同じ1キロのゴミでも内容次第でポイントが違うため、時間内にどこを回ったら目的のゴミを多く拾う事が出来るかルート戦術も重要になってきます。今年は、小野会長をはじめとする理事チームも初めて結成され、活気あふれる大会となりました。
今年は、全チーム合計で182kgのゴミが回収され、過去最高を記録しました。優勝したのはWOWOWとWOWOWプラスの合同チームとなり、大会2連覇を成し遂げました。準優勝は東北新社、第3位は第一興商が獲得しました。ことしは小野会長をはじめとする理事チームも結成され、表彰式では順位の発表に各チームが一喜一憂しながらも、会員社同士の交流も生まれた社会貢献活動となりました。
衛星放送協会では引き続き、社会貢献活動を推進して参ります。

| 実施年度 | 会場 | 参加社 | 回収ゴミ総重量 |
|---|---|---|---|
| 第1回(2014) | 赤坂 | 22社 81名 | 86kg |
| 第2回(2015) | 青山 | 21社 96名 | 122kg |
| 第3回(2016) | 青山 | 24社 116名 | 134kg |
| 第4回(2017) | 神宮外苑 | 雨天中止 | |
| 第5回(2018) | 赤坂 | 20社 107名 | 101kg |
| 第6回(2019) | 赤坂 | 21社 113名 | 182kg |
| 開催日時 | 2019年10月26日(土) |
|---|---|
| 会場 | 東京都港区・赤坂一帯 |
| 参加社数 | 21社113名 |
第25回 衛星放送協会倫理委員会・CAB-J共催セミナー
2019.11.27

総務省 坂本氏
10月31日(木)に衛星放送協会において、第25回 衛星放送協会倫理委員会・CAB-J共催セミナーが開催されました。今回は、2年ぶりに改定された総務省「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(第6版)改定のポイントがテーマ。本セミナーを通して下請法や独占禁止法などをベースとするガイドラインへの理解を深めるとともに、より一層の番組製作における適正取引促進を目的として実施されました。
講師には一般企業法務が専門の小林直弥弁護士をお招きするとともに、本講義に先立ち、今回のガイドライン改定の主幹となった総務省 情報通信作品振興課の坂本主査にもご登壇いただき、ガイドライン改定の経緯や今後の総務省の取組みをお話しいただきました。

小林弁護士
講義は「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(第6版)に沿って行われ、ベースとなる下請法、独占禁止法、著作権法などの関係法令の解説からはじまり、改定のポイントとして留意すべき、「取引価格の決定」、「番組の著作権帰属」に関する放送事業者と番組製作会社との事前協議および「書面交付」の重要性、「取引内容の変更・やり直し」に関する留意事項が話されました。また、今回の改定で強化が図られたベストプラクティスも交えた解説となり、番組製作における適正取引について、放送事業者が理解をより深めることができたセミナーとなりました。
また、今回のセミナーでは会場が満席となる44名の方が受講された他、質疑応答では、日ごろ抱える実務に即した質問がなされ、会員社の関心の高さがうかがえました。
■ご参考)「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000123.html

| 開催日時 | 2019年10月31日(木)13:30~15:30 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 講師 | 小林直弥弁護士(大江橋法律事務所) |
| 参加社数 | 23社 44名 |
著作権委員会・2019年度著作権セミナー
2019.10.07

前田哲男 弁護士
拡がりを見せるOTT動画配信サービスでの放送コンテンツの提供、今年度中にも開始される見込みであるNHK常時同時配信など、通信を介した放送コンテンツの提供の多様化が進む現状を踏まえ、2019年度の著作権セミナーは、弁護士の前田哲男先生をお招きして『放送コンテンツの二次利用における課題整理と展望』と題した講演会を開催いたしました。
協会員各社から様々な部門の担当者が参加され、関心の高さがうかがわれました。
公演前段では、現行の著作権法の条文に基づいて“「放送」についてのみ権利処理が不要とされること”について解説され、配信における権利処理との違いを明確化。
その上で、日本法と世界知的所有権機関(WIPO)における「放送の同時配信」「ウェブキャスティング」「見逃し配信」の位置付けを解説され、“「放送」のルールを「配信」にまで拡大すべきか”というポイントについてお考えを述べられました。
公演後段では、放送番組を制作する上で理解が重要となる「ワンチャンス主義」について条文に基づいて解説され、“「配信」の為に製作されるコンテンツにも主義が適用されないか”とのポイントについて整理頂きました。
現在、関係機関において「同時配信に係る著作権処理の円滑化の推進」について議論が進められておりますが、これらの議論の方向性を正しく理解する上でも、参考となる講演内容となりました。

| 開催日時 | 2019年9月12日(木)13:30~15:00 |
|---|---|
| 会場 | 明治記念館 若竹の間 |
| 参加社数 | 98名(49社) |
青少年健全育成活動「テレビ番組のイベント現場を親子で体験しよう!」
「LIVEHOLIC extra vol.3」
2019.04.17

衛星放送協会の倫理委員会では、青少年健全育成活動として、新小学4年生~新中学3生とその保護者を対象に 『テレビ番組のイベント現場を親子で体験しよう!』を開催しました。
9回目となる今回は、趣旨にご賛同いただいた衛星放送協会会員の株式会社スペースシャワーネットワークにご協力頂き、3月30日に幕張メッセイベントホールで行われたライブイベント「LIVEHOLIC extra vol.3」を親子で収録施設の見学とお仕事体験をして頂きました。
公募で選ばれた5組の参加者に冒頭、衛星放送協会側から活動趣旨と衛星放送について説明した後、スペースシャワーネットワークのイベントご担当者にスペースシャワーネットワークと今回の「LIVEHOLIC extra vol.3」の概要を説明頂きました。

今回のライブの模様は 後日スペースシャワーネットワークで放送されるため会場内には収録機器が設置され、技術スタッフの方から収録体制、スタッフの役割、放送までの流れについて説明を受け、参加者は実際にカメラの映像を切り替える機器を操作しながら各カメラの役割を確認することができました。

質問コーナーでは「放送する際の曲目はアーティストが決定するのか?」など多くの質問が出され、放送の仕事を理解する機会となりました。

受け取ったお客様は小さなスタッフに驚きながら、「ありがとう!」と温かな言葉を返し、その場はとても和やかな雰囲気になりました。そして、ライブの開演前にお仕事体験は無事に終了しました。

衛星放送協会では、青少年が将来に向け大きな夢を持ち、職業人となる自覚を高めてもらうことを願い、青少年健全育成活動を実施しております。今後も、このような番組制作の現場体験を様々な形で継続して参ります。
| 開催日時 | 平成31年3月30日(土)11:00~13:00 |
|---|---|
| 場所 | 幕張メッセイベントホール (千葉市美浜区中瀬2-1) |
| 内容 | 音楽ライブ 「LIVEHOLIC extra vol.」の会場で、番組収録の設備見学と、受付業務を体験 |
| 参加者 | 親子4組(新小学4年生~新中学3年生と保護者) |
第24回倫理委員会・CAB-J共催セミナー
2019.03.26

山口純也氏
24回目となる衛星放送協会倫理委員会・CAB-J共催セミナーが、3月15日(金)に衛星放送協会会議室にて開催されました。今回は倫理委員会 副委員長として、後述の「放送コンテンツ適正取引推進協議会」に参加されている、スカパーJSAT株式会社 放送営業部 業務管理チーム長の山口純也氏に講師をお願いし、『「よくわかる放送コンテンツの適正取引」-番組製作における下請法のポイントを業界及び行政の動向を交えて-』と題して、放送の番組製作における適正な取引の一層の促進をテーマに実施されました。
2003年に下請法が改正されて、放送コンテンツの製作においても、より適正な取引の促進が求められることになり、総務省による「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の策定、公正取引委員会による実態調査も行われ、問題点と対応が整理されてきた経緯が説明されました。
その中で、2018年から総務省が開催している「放送コンテンツの適正な制作取引の推進に関する検証・検討会議」の中で、「ガイドラインの見直し」など適正化に向けた措置が検討され、衛星放送協会も参加する「放送コンテンツ適正取引推進協議会」によって「よくわかる 放送コンテンツ適正取引テキスト」が作成されたとのこと。同テキストは、「課題の認識」「法令の基本的な理解」「番組製作場面での法令理解」「法令順守の具体的な対応と仕組みづくり」によって構成されており、それぞれについて、順を追ったポイントの解説を頂きました。
また、各所における適正取引啓蒙活動や、会員社の活動例も紹介され、一層の下請法の理解と、継続した適正取引への取組みにおいて、今後の具体的行動の参考となる講演内容でした。
同テキストは衛星放送協会ホームページ『情報公開』に掲載してありますので、社内でぜひご活用下さい。
| 開催日時 | 平成31年3月15日(金)14:00~15:00 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 講師 | スカパーJSAT株式会社 放送営業部 業務管理チーム長 山口純也氏 |
| 参加社数 | 15社 24名 |
第13回人材育成セミナー
2019.02.27

油布顕史氏
総務委員会では、2月14日 「第13回人材育成セミナー」を開催しました。
今回は地上波を主体とする放送局の人事制度改革に数多く従事された、KPMGコンサルティング株式会社ディレクター油布顕史氏をお迎えし『人が育つ職場のつくり方 ~今日から取り組む新しい働き方』をテーマに講演いただきました。
昨今の「人口減少」「テクノロジーの進化」「高年齢化」の背景の中で、今年4月に施行される「働き方改革関連法」では、「長時間労働の是正」「正規と非正規の待遇差の是正」等が課題となっています。
今年4月より順次施行される「働き方改革関連法案」を解説された上で、これからの「働き方改革」の課題についてお話いただきました。
講演要約
企業は「働き方改革」の施策として、労働条件・業務プロセスの見直しや、テレワーク・サテライトオフィス、テクノロジーの活用、フリーアドレス等の職場環境の改善等を導入しているが、これらのルールや仕組みを導入しただけでは改革の実態に合っていないように見える。「働き方」は社員によって捉え方が違うので、施策のプロセスをしっかり把握したうえで、会社が抱える問題を全体的・立体的に捉えながら段階的な導入が望ましい。
また働き方改革の本質でもある、「生産性の向上」「人材活用」「イノベーション」について、今の企業の取り組みは「働きやすい」環境整備に偏っていて、「働きがい」が軽視されている。仕事の達成感やチャレンジといった従業員の成長に繋がる「働きがい(=満足の向上)」に手を打てていない企業が多い。
環境要因である「働きやすさ(=不満の抑制)」は、人間の欲求の本能であるが一過性でしかない。満足を高める施策、動機づけの要因となる「働きがいの創出」が重要となる。そのためには、働き方の多様化に対応できるマネジメントの変革進化が課題となり、経営者と従業員が一体になって取り組む問題である。
従来の人生モデルは3ステージ(教育⇒仕事⇒リタイア)だったが、これからは人生100年時代になり、仕事をリタイアするまでの期間が延びて80代まで働く時代がやってくる。その一方で、AI(人口知能)が発達し、過去データの積み重ねで判断できる形式的な業務はAIにとって代わられる。
これからのマルチステージな人生モデルを設計するには、機械には置き換えられないスキルを身につけることが大切となり、社交力(良好な人間関係)、問題解決力(論理的な考え)、認知力・認識力(積極的な傾聴・他人にものを教えられる)、状況判断力(ものごとを柔軟にとらえる)を持った人材が必要とされる。
職場には5世代(20代~60代)にわたる従業員が存在し、各世代が経験した時代やライフステージに伴って仕事の動機やキャリアの価値観も異なっている。その中で従業員それぞれのエンゲージメント(従業員が主体的に組織貢献を行う意識行動)を高める施策を揃えてマネジメントしていくことが求められている。そうしたことが、組織の生産性向上やイノベーションを達成する企業成長のカギとなる。
長寿化の中で今までのような働き方では80歳まで働き続けることは限界があり、従業員も姿勢を変えていく必要がある。「働き方改革」とは企業の問題であると同時に従業員が自分事として考えていく問題でもある。

| 開催日時 | 平成31年2月14日(木)16:00~17:30 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 参加社数 | 19社 34名 |
第23回倫理委員会・CAB-J共催セミナー
2019.02.18

山本一広専務理事
第23回となる倫理委員会・CAB-J共催セミナーが、2月5日(火)に衛星放送協会会議室にて開催されました。公益社団法人日本広告審査機構(JARO)の山本一広専務理事を講師にお迎えし、「広告・表示のフェアプレイ-適正な広告・表示を実現するために-」をテーマに講演を実施していただきました。
2018年度上半期におけるJAROでの総受付件数は5,237件で、これは前年同期比99.1%。うち苦情が3,911件(同101.8%)、照会が830件(同98.0%)、広告以外が426件(同71.7%)となりました。件数自体は減ったものの一般消費者からの苦情は増加傾向でテレビ・インターネット2媒体に対するものが大きな割合を占めました。業種別でみるとデジタルコンテンツ等が前年同期に引き続き1位、インターネット上で展開されるコンテンツ・サービスの拡大の影響によるものと考えられるとのことでした。
総受付件数5,237件のうちJAROの審査対象となり見解が出された件数は14件、対象媒体ではインターネット広告が7件と依然一位ではあるものの前年同期14件から半減したのに対し、前年1件だったテレビは6件となったとのことでした。改めてテレビ業界の広告表示適正化に対する理解度が問われる結果となりました。
消費者庁の措置命令に合わせて課徴金が課される例が多くなる、広告・表示に関しても特定商取引法を適用し通信販売事業者に業務停止命令が出されるなど悪質な事業者に対する規制が厳しくなっています。テレビCMにおいても、「個人の感想です」が打消し表示となるので何を言わせても良いという言い訳はもはや通用せず、不当表示と認定されるケースも多くなってきています。仮に有用でない商品が不当表示で売れたとしても、長続きはしませんし、広告業界の公正な発展にも決してプラスにはなりません。考査や広告の適正化が消費者保護だけではなく広告主の健全性を担保することにつながり、延いては広告業界の健全な発展に寄与することになるという講演内容でした。
| 開催日時 | 平成31年2月5日(火)14:00~15:00 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 講師 | 公益社団法人日本広告審査機構 専務理事 山本一広氏 |
| 参加社数 | 20社 31名 |
小野会長 2019年 年頭あいさつ
2019.01.18
小野会長 2019年 年頭あいさつ

一般社団法人衛星放送協会
会長 小野直路
新年明けましておめでとうございます。
衛星放送協会は昨年6月に新体制をスタートさせました。2018年度の重点目標として「有料・多チャンネル放送市場拡大への取り組み」を掲げ、以下の活動をしております。
放送の高度化が前進
東経110度CS右旋放送のハイビジョンチャンネルは、これまで全54チャンネル中、21チャンネルでしたが、昨年10月までに新たなチャンネル・ラインナップによる東経110度CS放送が開始され、42チャンネルに拡大し全体の80%がハイビジョン化しました。
また、昨年12月1日には新4K8K衛星放送がスタートし、衛星放送協会の会員社からは13チャンネルで開始されました。4K対応テレビの累計出荷台数は500万台を超え、対応チューナー内蔵型受信機も各社から出揃い、これから普及に弾みがつくものと期待しています。また、ケーブルテレビ経由では新たにアンテナを設置する必要がないため、更に力強くけん引していただけると期待しています。衛星放送協会では、視聴者に魅力的なコンテンツを訴求し、視聴方法の正しい知識の周知広報を今後も継続的に実施して参ります。
有料・多チャンネル放送の契約数
2018年11月末の契約数は、1,361万件となりました。前年同月は1,350万件でしたので、この1年でみると11万件の増加となりました。有料・多チャンネル放送は端的に言うと踊り場に踏みとどまっている状況ですが、新4K8K衛星放送といった新しいサービスを起爆剤に、それぞれのプラットフォームとも連携し、更なる成長を図りたいと考えています。
BS右旋/左旋及び110度CS左旋の放送拡充
この程、総務省から衛星基幹放送への新規参入に係る公募が発表されました。現在、「放送法関係審査基準改正案」の意見公募が行われており、衛星放送協会としても会員社としっかり情報を共有しながら、機の逃さず提言して参ります。新規参入の公募はこの3月までに行われ、夏頃に認定され、来年の夏から秋にかけて新たな放送の開始が予定されており、今年は市場の拡充に向けた大きな節目になるものと考えています。
NET社会への対応
動画配信サービスの多様化が進む中で、現在、衛星放送協会の会員社の中でも、独自に配信サービスを立ち上げている事業者が登場しています。今後、有料・多チャンネル放送市場を更に拡大し発展させるために、動画配信プラットフォームは協調、連携していく重要なパートナーだと考えています。
「第9回衛星放送協会オリジナル番組アワード」授賞式
そして、成長の鍵を握るのは、専門チャンネルの強みを生かしたオリジナルコンテンツによって存在感を示すことが不可欠です。衛星放送協会では会員社のオリジナル番組制作を促進し、その取り組みや優れた番組を広く知って頂くため、今年の7月17日(水)よみうり大手町ホールにおいて「第9回衛星放送オリジナル番組アワード」授賞式を開催します。
広告出稿獲得の強化と、有料・多チャンネル放送の将来像
当協会の附属機関である衛星テレビ広告協議会(CAB-J)では、広告出稿の獲得強化に取り組んで参ります。また、昨年に設立10周年を迎えた多チャンネル放送研究所は、有料・多チャンネル放送の将来像について今後も調査、分析を継続して参ります。
衛星放送協会では、2019年も有料・多チャンネル放送が社会の信頼に応え、輝く1年とな るよう関係団体とも連携を図りながら努力を重ねて参ります。会員社の発展に向けて、制度 面の支援やオリジナル番組の制作推進などを通じてその一翼を担いたいと考えております。 今後の協会活動にご理解をいただきますようお願いして、私のごあいさつといたします。
多チャンネル放送研究所 設立10周年記念シンポジウム
~これからの多チャンネル放送はどこに向かうのか~
2019.01.18
多チャンネル放送研究所は2018年に設立10周年を迎えました。これを記念し、2018年11月20日(火)に 明治記念館において「設立10周年記念シンポジウム」を開催いたしました。

今回のシンポジウムでは、従来より毎年行っている研究員による 研究活動報告に加え、総務省情報流通行政局長 山田真貴子様の 基調講演/インタビュー、そして、映像関連分野の第一線でご活躍されて いる3名の外部の方々をパネリストとするパネルディスカッションを 行いました。その概要は以下のとおりです。
■ ユーザー分析WG
主査:清正 徹

清正 徹 ユーザー分析WG主査
2017~18年の2年に渡り、現在のユーザーの映像視聴実態を調査し、10年前から何が変わったのか、これから、映像はどのような見方をされていくのかを探った。2017年発表会の中間報告では、同年6月に実施した事前定量調査をもとに「映像親密層」、「先進層」、「情報関心層」、「低関心層」の4つのセグメントでユーザーを分析したが、同じ「先進層」でも映像への接し方、選択の仕方も異なることが分かった。このため、「映像環境の多様化が進み、各セグメントの中で視聴は更に階層化している」という仮説を立て調査・分析を行った。
2018年6月に実施した定量調査で各映像サービスの浸透度をみると、認知率ではサービスの歴史から多チャンネル放送の認知率が高かったが、興味・利用率ではAmazon Prime Videoの台頭が目立った。
Amazon Prime Video利用者への行動観察調査では、「動画サービスに対する情報収集は事前に行わない」、「加入のきっかけはショッピングやコストパフォーマンス」、「気にならない価格のため、さほど視聴しなくても「料金は高く感じられない」」という傾向がみられた。
一方、多チャンネル放送を以前から利用しているユーザーへの行動観察調査からは、「テレビをみるのが好き」、「家族でテレビをつけっ放しで視聴する」といった昔ながらの視聴スタイルが伺えた。
また、多チャンネル放送とOTT両方利用されているユーザーからは、画質、コンテンツ、価格の比較において、多チャンネル放送から、徐々にOTTのほうに視聴が移りつつある傾向もみえた。「みたいコンテンツがOTTに集まっているとユーザーが感じている」、「映画、韓流といったこだわりのコンテンツをみたい時にじっくりみたい、というタイムシフト化がスポーツ以外のコンテンツで進んでいる」等が主な理由である。
定量調査で、「併用しているサービス」をみると、Amazon Prime Videoは、多チャンネル放送、OTTサービス利用者ともに高い併用率となっており、今後、各サービスからAmazon Prime Videoに流出する可能性も考えられる。「過去利用サービス」においては、放送ではWOWOWから、OTTではHuluから別のサービスへの流出が目立った。
多チャンネル放送とOTT加入者の映像に対する価値観をみると、ライブ視聴以外はOTT加入者の方が映像に関する意識は高くなっている。一方、加入意向者については、多チャンネル放送、OTTのどちらもほぼ変わりなく、今後どちらに加入するかはメッセージの到達次第と考えられる。
また、今後どのようなサービスが魅力的に映るのかをグループインタビューで確認すると、「少しでも新作が多い」、「今まで見たことがないような体験を映像を通してしたい」という、「新鮮さ」や「今までにない体感」を望む声が多かった。
定量調査の結果の通り、ユーザーのサービスの選択基準は「みたいジャンルがある」という理由が最大であることには間違いないが、「何を」だけではなく、「どうやって」みせるかの工夫、つまりメディアとしての「新鮮さ」が差異化に繋がるのではないかと推察する。ただし、グループインタビューからは、「外出から録画予約ができる」、「持ち出して視聴できる」、「画質が良い」は既に出来て当たり前とされ、この程度では差異化にならず、さらに強いインパクトが不可欠と思われる。
サービスの選択肢が多様化する中で、これからの多チャンネル放送が、ユーザーに興味を持ってもらい、活用し続けてもらうためには、「新鮮さ」を常に醸成させる見せ方の追求が必要であると考える。
今後も多チャンネル放送研究所では、引き続きユーザー視点の調査を行っていきたい。
■ 将来像予測WG
主査:三塚 洋佑

三塚 洋佑 将来像予測WG主査
多チャンネル放送事業者の収支状況については、ネット収入が前年調査結果より微増となり、営業損益で黒字となった事業者の割合は過去3年間で最高となった。一方で、前年より「減益となった」との回答は増加しており、黒字ながらも利益幅が減少している事業者が多くなっているものと考えられる。また、費用面では、前年に続き「オリジナル番組の制作」、「コンテンツ強化」など、編成強化に向けた番組制作費・購入費を増強したと回答する事業者が多くなっている。
多チャンネル放送サービスの加入者数予測は、今後3年に渡りスカパー!、CATV、IPTVいずれも横ばい、スカパー!プレミアムサービスは引き続き減少傾向、との見方が多数を占め、厳しい見通しとなっている。その中で、最も重視するプラットフォームとして「モバイル/PC等向け配信プラットフォーム」を挙げる事業者の数が「CATV」と並んで最も多い結果となった。実際具体的な取り組みを開始している事業者も前年より大きく増え、スカパー!やIPTVはその後塵を拝している。3年後の加入者数予測に影響を与える要素としても、大半の事業者がインターネット映像配信、いわゆるOTTサービスを挙げている。一方で、4K/8K、およびTVの大型化への関心はやや後退している。
OTT市場の拡大は、スマホやタブレットのコモディティ化に伴い、確かに多チャンネル放送市場に少なからず影響を与えているものと考えられるが、今後も新たなデバイスやテクノロジーの進化が、ユーザーの映像視聴スタイルに変化をもたらす可能性がある。その中で、新たな視聴体験の提供を可能にしうるものとして、「VR/AR」、「AI技術・ビッグデータの活用」を取り上げ、様々な事業者の取り組みなどをヒアリングしつつ考察した。
VR/ARについては、今後3年間で市場規模が数千億円規模に伸びていく予測であるものの、現時点では実態として伸びているとの実感はなく、各社トライ&エラーを繰り返しており、コンテンツ単位での収益化にはほとんど至っていない。VR/ARコンテンツの制作、運用は費用・訴求力の面でも一チャンネル事業者が担うには難しく、コンテンツ制作能力・専門性の高い企画力を活かした比較的小さな取り組みから始めていくことが必要であろう。
AI・ビッグデータについては、既に字幕生成やダイジェスト版の自動制作など、映像分野での活用が進んできている。今後さらに、視聴者への番組や出演者の情報提供や、ターゲットに合わせた広告展開など、効率化やコスト削減、新たな番組視聴体験に寄与できる可能性がある。多チャンネル放送市場全体でのメタデータ等のビッグデータ活用が、新たな攻め手・打ち手となり、視聴者数や広告などの収入拡大に繋げられるのではないか。
こうした「AR/VR」、「AI・ビッグデータ」のような新しい技術は、必ずしも予測どおりに普及していくものではないかもしれないが、これらを活用することで、多チャンネル放送が持つ専門性の高い番組の面白さを改めて視聴者に認知させ、市場の再度の発展につなげていくことができるかもしれない。
■ コンテンツ論WG
主査:神崎 義久

神崎 義久 コンテンツ論WG主査
各社の「オリジナル番組制作の取り組み」について、実態調査からは次のような傾向が表れた。①オリジナル番組の強化に取り組む事業者は年々多くなっている。各チャンネルは、専門性を高めることにより認知拡大・加入促進を図りつつ、収益機会の増大を狙っている。②一方、投下費用の回収策として、従来のプラットフォーム(PF)に加え、OTT事業者との連携を年々拡大していたが、あらためて既存PFとの連携強化の意識が高まっている。③また他チャンネルやOTT事業者への番組販売による増収には一定の成果があるものの、それ以外の増収策がなかなか伸びず苦戦が続いている状況も見られる。
同じく実態調査による「4K・8Kへの取り組みについて」という点では、積極派は、まずはプラットフォームとの共同制作や番組販売等の取り組みを進めているが、費用面での課題は残っているようだ。消極派は、コストとニーズあるいは他社の取組みなども見ながら検討するという姿勢と、4Kが普及するかという点で懐疑的な意見の2極化が見られた。
また、株式会社三菱総合研究所社会ICTイノベーション本部の高橋副本部長、ICT・メディア戦略グループの伊藤様、牧山様、そして株式会社インフォシティ代表取締役の岩浪様にご協力いただき、国内外の市場環境、さらに5GやAIが放送業界に与える影響などのお話を伺った。詳細は別途報告書に記載するが、高橋様、岩浪様ともに、既にスマホは完全に生活習慣の一部だと位置づけ、有料放送を含む放送サービスが今後も生活習慣として生き残るためには、この領域への展開が不可欠との提言をされていた。
こうしたことから、多チャンネル放送業界を取り巻く環境は、テレビ視聴が生活習慣として定着しているものの、スマホをはじめとする動画を見るデバイスが急速に多様化し一般化するにつれ、利用者はデバイスを選ばず、放送や配信やチャンネルも区別せず好きなコンテンツを楽しむ、しかもデバイス上で決済までできるという変化が加速する。テレビを見る習慣がある今こそ、この急激な変化に対応する方策に取り組まなければならないと考える。有料放送として生活者にどのようにアピールしていくのか、早急な対応が今後ますます問われるだろう。
【記念シンポジウム】
これからの多チャンネル放送はどこに向かうのか
■基調講演/インタビュー
総務省情報流通行政局長 山田 真貴子様 (進行役:多チャンネル放送研究所 所長 音 好宏)

音 好宏 所長
山田局長には、音所長とのセッション形式で講演いただきました。冒頭、放送メディアの市場規模から有料多チャンネル市場についてデータをもとに現状をまとめていただきました。その上で、ネット動画配信は非常に伸びてきている。広告市場は、インターネットが大きく増え、テレビが横ばいないし微減。広告市場としては、欧米はとうの昔にテレビをインターネットが抜いており、日本も近づいてきつつある雰囲気、まだテレビのほうが視聴としては大きいが、こういう傾向にあるということは押さえておかなければいけない。と述べられました。
多チャンネル放送のサービス内容をどんなふうにお感じになり、また評価されているのでしょうか

山田局長
日本の多チャンネル放送サービスは、新しい世界を開いて、価値あるコンテンツを有料で見るという新しいモデルを導入し、一定程度、定着しています。特に3波共用になって視聴可能性が広がり、非常にいい状況になってきている中、ネットのチャレンジが来ている時代になっています。24時間しかない中で自分の時間をどう使っていくかというところで、より魅力あるコンテンツ、あるいは簡便な視聴が問われている時代になっているのではないかと感じています。
コンテンツのことでいうと、4Kコンテンツの充実は不可欠ですが、この取り組みをどう進めたらよろしいでしょうか。
高画質化というのはチャレンジすべき、しかも放送にしかできない重要な要素ではないかと思います。世界的にも4Kへの大きな流れがありますので重要な要素としてチャレンジしていく必要があります。4Kというチャンネルができるので、ピュア4Kをどんどんふやしていくことを各放送事業者にまずは努力していただきたい。ピュア4Kというものをつくったときに一体どんな世界が広がって、何が魅力的なのか。まだチャレンジの世界だと思いますがノウハウが高まって、本当にいい、日本ならではの4K文化みたいなものができていくことを期待しています。
多チャンネル放送市場の発展がもう少し掲げられて、その上でプラットフォームと多チャンネル事業者の共通した取り組みができればいいのではないかとも思うのですけれども、そのあたりに関してはどのようにお考えになっていますでしょうか。
総務省の中に「放送を巡る諸課題に関する検討会」があって、「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」で、これからの未来像みたいなものを、検討しました。その中で、BS、CS、それの右、左旋について、改めて整理をし、新規参入も考えていく必要があるということ、高画質化に取り組むべきではないかということ、全体としての魅力を高める中で加入者が増えマーケットとして大きくなることを目指していくということを大きな目標として、さらなる活性化を図っていきたいということで、レポートをまとめました。総務省としても、有料多チャンネル市場をもっと発展させたいということについては、全く異論なく、皆さんと一緒にやっていきたい。業界全体の発展のことを考えたときに、何ができるのかということを全体として考えていただく時期に来ていると思っています。
【パネルディスカッション】
(パネリスト)
株式会社インフォシティ 代表取締役 岩浪剛太 様
BuzzFeed Japan株式会社 動画統括部長 福原伸治 様
慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所 教授 鈴木秀美 様
(モデレーター)
多チャンネル放送研究所 所長 音 好宏
音――まずは今の多チャンネル放送に対して問題提起を。

左:福原氏、右:岩浪氏
(岩浪)テクノロジーとユーザー。今、あらゆるビジネスがこの二つの変化でいろいろと変わってきている。アメリカでは、テレビがインターネットで伝送されつつあり、Netflixなどもスマホで見る割合が増えている。また、スマホはお金を払う機械と化しており、全世代にわたって普及している。
5Gは20ギガの超高速・多数同時接続・超低遅延で2020年キックオフ。WiFiも次の規格が出る最中で、最大9.6ギガ。これが普及すると、あらゆるビジネスが変わっていくだろう。
(福原)テレビとネットのつくり方は似ているようで違うため、テレビをそのままネットに持っていっても通用しない。テレビは放っておいてもお客さんが来てくれるが、ネットはこちらからコンテンツを渡しに行く必要があり、データがより重要になってくる。もう一つは、ネットはグローバルであること。海外のプレーヤーとも戦わなくてはならないが、逆に日本のコンテンツも輸出できるという面がある。

左:音所長、右:鈴木氏
(鈴木)制度の観点からすると、放送法は、事業者に規制を課し、放送の公共性を確保しようとしているものだ。多チャンネル放送については、放送法による規制が果たしてきた役割を確認し、それを維持するのか、それとも緩和するのか。皆が考えていく必要があるのではないか。当初は技術的な制約に合わせて規制を加えていたものを、その制約がなくなりつつあるのに、今もなお規制を残している部分もある。
音――5Gの時代になり、スマホで放送的なものがどんどん手に入れられるようになる。その中で、放送とインターネット上での動画配信は、それぞれどう位置づけたらよいのか。
(岩浪)容量の大きな映像コンテンツがインターネットでデリバリーできるようになった。しかし、インターネット上のストリーミングサービスについては、地上波や衛星波の再送信を行っていないため、これをユーザーはテレビとは見なしていないと思う。ネットによるテレビやスマホへの同時配信が議論になっているが、それらも準テレビ(テレビもどき)という位置づけで、テレビの補完だと捉えてもいいのではないかという提言をしている。
音――多チャンネル放送が出ていく場所はもっとたくさんあるのではないのかということか。
(岩浪)伝送路もコンテンツもデジタルになり、コンテンツが経路を問わず出ていける時代になっているし、その出口は固定もインターネットもモバイルも含めて増えていく。その中で決定的に普及したのがスマートフォンでこれは非常に重要だと思う。
(福原)テレビであろうが何であろうが、ユーザーにとって意味があるか、おもしろいか、価値があるかということに尽きる。ユーザーが望むコンテンツをどうそれぞれのデバイスにあった形で作り分けて、最適な形で届けていくか。規制するばかりでなく、いかに発展させていくべきかを考えていかなければ、グローバルな競争相手に勝てないという危機感をもっと持ったほうがいいと思う。今の仕事は、テレビ時代の5倍ぐらいのスピードでやっている。海外はもっと早い。そういうところとテレビはどう戦っていくのかを考えなければならない。
(鈴木)放送法についていえば、これまでの改正も、当事者がこうしてほしいという要望が大きなきっかけにこれまでもなってきたはず。グローバルに競争しなければいけないときに、日本の法律が足かせになるのであれば、プレーヤー側から問題提起をしていくべきでしょう。CS放送も番組編集準則や番審設置の義務があり、これらが本当に必要なのかという論点はある。もっと放送としての自由度を高めるような制度に変えていく方向も検討できるのではないか。
音――番組作りに当たっての規制のありようについてはどんなふうに位置づけを。
(福原)これはつくり手の意識の問題が大きいと思う。番審があってBPOがあっても問題は起こる。制作者を教育することを考えるべきであって、規制があるから大丈夫だという考えは、逆に規律が緩くなってしまうのではと思う。
(岩浪)同じユーザーでも、テレビの前に座っているときとスマホを手にしてインターネットでなにか見ているときと、モードが変わっている。やっぱりそのモードを的確に捉えて、発信することが求められるのではないか。
(福原)視聴者を一人一人個性のある「ユーザー」と捉えて、彼らがどういうものを望んでいるのかをはっきりさせるためにビッグデータを活用していく、というのが鍵になってくると思う。
音――では、最後に多チャンネル放送の将来に向けてアドバイスを。
(岩浪)やはり、スマホというのは今までにない存在。ユーザーが全員、スマホを常に持ち歩いているという前提でビジネスをしたほうが良い。前述のように、スマホは決済手段としてお金を払ってもらいやすい端末だというのが大きな魅力。これからはスマホを中心にビジネスを考えたほうがよいのではと思う。
(福原)多チャンネル放送のほうがフットワーク軽く、地上波では出来ないことも出来るのではないか。そして、ネットとどう密接にやっていくか。ユーザーのデータをどうとって、コンテンツにフィードバックしていくか。そこを考えていけばよいのではないか。やはり、おもしろいもの、ユーザーの望むものを作るということに尽きる。
(鈴木)事業の足かせとなる不要な規制は不要ではないか。放送はその例外とされてきたが、フットワーク軽く事業を展開するためにも、果たして今後も例外扱いでいいのだろうか。そこの問題意識をもつことが重要だと思う。
音――今回のパネルディスカッションでは、多チャンネル放送に直接かかわらないお3方を招いて、いま世の中がこんなに動いているというお話、そして問題提起をして頂いた。
この中で重要なことは、「自分の未来を自分で決める」、ということではないか。一つは、衛星放送協会にかかわる会員社で力を合わせて、業界として未来を考えること、もう一つは、個々の会社、それからそこで働いている個々人が、自分たちのかかわっているサービスの未来を、自分で考えて自分で決めるということだ。(了)
| 開催日時 | 平成30年11月20日(火)13:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 明治記念館(港区元赤坂)「曙の間」 |
| 参加社数 | 62社 130名 |
衛星放送協会について
- 衛星放送に関するプラットフォーム
業務に係るガイドラインに基づく委員会 - 普及促進委員会
- 衛星放送のプラットフォーム
ガイドラインに関する委員会