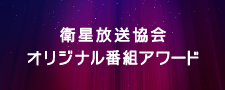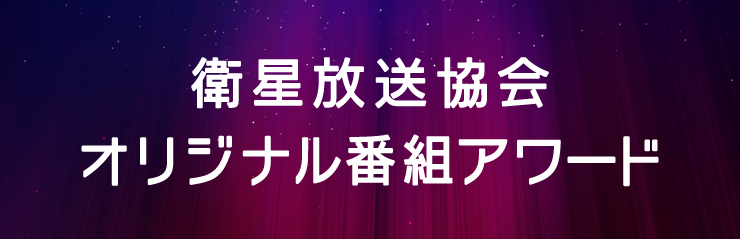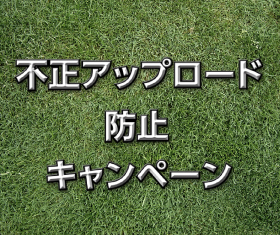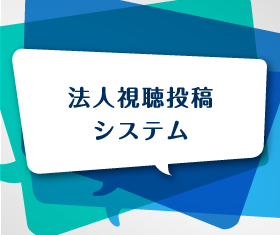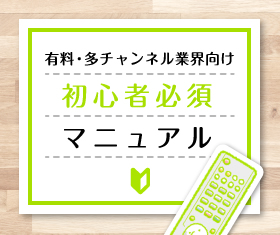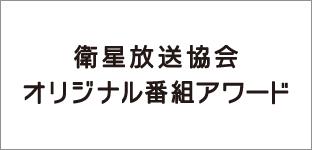活動報告
2018年
技術委員会主催の情報セキュリティセミナー開催
2018.12.27
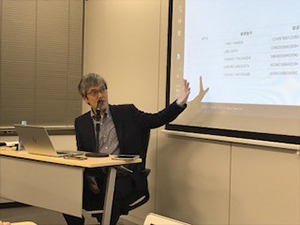
徳丸浩氏
12月13日、技術委員会主催の情報セキュリティセミナー『Webセキュリティ入門講座』が開催されました。
講師にEGセキュアソリューションズ株式会社代表取締役徳丸浩氏(著書に『体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方』など)をお迎えし、Webサイトの構築・運用にあたり知っておくべき基本的な事項と、サイバー攻撃に備えたサイト制作・管理上の対策ポイントをご説明いただきました。講義では「Webサイト攻撃のトレンド」「Webサイト攻撃の具体例」「Webサイトのセキュリティ診断とその重要性」「Webサイト作成・管理の工程別ポイント」の4つの項目に分けて学びました。
最初の項は「Webサイト攻撃のトレンド」。脆弱性の公開から攻撃までがスピードアップされ‘猶予期間’が短くなり対策が間に合わないケースが多くなったこと、著名ソフトウェアの脆弱性を狙った事例が目立つこと、攻撃者の狙いが多様化している(個人情報の窃取、サイト改ざん等)ことなどが挙げられました。
次に「Webサイト攻撃の具体例」。ロシア政府のWebサイトが仮想通貨マイニング目的でクリプトジャックされた例、化粧品ブランドのIPSAがECサイトにバックドアを設けられて個人情報(42万1313人分)を窃取された例、日産グループ会社のWebサイトがDDoS攻撃された例、丸川珠代参議院議員の公式サイトがAPI機能を使った攻撃を受けた例など、政府・企業・個人と、攻撃対象から目的・手法まで多種多様な具体例が示されました。今治タオル販売事業の伊織の通販サイトで発生したクレジットカード情報窃取(2145人分)の手口は、意図しないサイトにアクセスしたこと自体を利用者に気付かせないという手法は脅威でした。これに気付く手段として、ページが切り替わったらURLの頭を見るというアドバイスは大きな収穫となりました。脆弱性を再現したサイトを使用した攻撃のデモも行われたため、攻撃の速さを含めて体感的にも理解しやすいものでした。
続く「Webサイトのセキュリティ診断とその重要性」は対策関連。先述の通り攻撃されたら対策が追い付かないため、実際にはサイトを立ち上げる前の準備が一番重要ということです。運用開始前に専門会社へセキュリティ診断を依頼して実施するのが有益ですが、‘診断’とは言っても攻撃を回避できるか、セキュリティホールがないか等を調べるため実際に‘攻撃’することになるため、リスク管理の観点からステージングサイト(検証サイト)を構築して行うこと望ましいとのことでした。
最後の項目は「Webサイト作成・管理の工程別ポイント」で、企画時、受入時、運用時、緊急時と工程別に説明いただきました。発注後のセキュリティ強化指示はすべて追加予算となるため、早い段階でセキュリティ面を重視しておいたほうが経済的とのことです。最初から仕様を指示RFPに盛り込んでおけばベンダー各社の競争原理を引出し、経費抑制も期待できます。Web制作を発注するベンダーの選択がセキュリティを左右する(ベンダー選びで7割決まる)とのことでしたが、ベンダーの見極め方は難しいため、一例としてベンダーのセキュア開発ガイドラインの提出を申し入れ、提出された文書が既成のサイト(「安全なWebサイトの作り方」など)の文言を丸写ししたものかどうか比較してみるのも有効とのことでした。またセキュリティ要求の定義とチェックシートを作成し、受入検収時の確認事項とする、予め脆弱性診断を実施する(脆弱性が見つかった場合にバグとして追加料金なしに対処してもらう)旨を伝えておくなど、初期段階で注意しておくべき点が列挙されました。運用時のポイントも契約内容によるため、先を見越した契約が必要とのことです。緊急時のインシデント対応については、予めインシデント発生時の連絡体制や権限の所在を取り決めておく、追加の防御策としてWAF(Web Application Firewall)の利用、改ざん検知システムの導入などについての説明がありました。サイバー攻撃は重大な経済的損失を被る可能性もあるため、初めから専門会社を活用することは費用対効果の面で非常に有効な手段とのことでした。
講義終了後は受講者からの質疑応答の時間が設けられ、細目なパスワード変更の是非やサイバー保険の有用性といった具体的な質問から、担当者に必要とされる知識はどれくらいか、といったWeb制作現場の生の声まで発せられ、最後まで熱気あるセミナーとなりました。
| 開催日時 | 平成30年12月13日(木)16:00~17:30 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 参加社数 | 23社 38名 |
社会貢献活動「第5回スポGOMI大会」
2018.10.22
衛星放送協会では、2014年から社会貢献活動の一環として「スポGOMI大会」を実施しています。スポGOMI大会とは、日本スポGOMI連盟が定めるルールに沿って行い、ゴミ拾いにチーム競技を取り入れ、ゴミの種類(缶、瓶、吸い殻など)の違いでポイントを競い順位を決めるもので、楽しみながら社会貢献する活動です。
今年は、10月20日(土)に東京メトロ赤坂駅から徒歩2分に位置する港区立氷川公園を拠点に、晴天のなか会員社107名が参加して行われました。
2014年の第1回大会ではゴミ収集量86kgでしたが、今回は101kgものゴミを集め、地域の美化に貢献しました。競技終了後の表彰式では、順位発表に各チームが一喜一憂しながら、会員社の交流も生まれた社会貢献活動となりました。
衛星放送協会では、今後も社会貢献活動を実施して参ります。
- 優 勝:
- 株式会社WOWOW/株式会社WOWOWプラス(合同チーム)
- 準優勝:
- スカパーJSAT株式会社
- 第3位:
- 株式会社第一興商

| 開催日時 | 平成30年10月20日(土) |
|---|---|
| 開会式 | 東京都港区立氷川公園 |
| ゴミ収集エリア | 東京都港区 赤坂一帯 |
| 参加 | 衛星放送協会会員20社 107名 |
青少年健全育成活動 春休み テレビ番組の制作現場を探検しよう!
~世界最大級のテレビショッピング専門チャンネル・QVCの舞台裏を見学しよう~
2018.04.03
衛星放送協会の倫理委員会では、青少年健全育成活動の一環として、新小学5年生~新中学生とその保護者を対象に「テレビ番組の制作現場を探検しよう!ツアー」を開催しました。
8回目となる今回は、本企画にご賛同いただいた正会員社の株式会社QVCジャパンにご協力を頂き、公募で選ばれた5名の小・中学生とその保護者に、QVC社屋設備・番組放送スタジオ・コールセンター等を親子で見学・体験していただきました。
冒頭に、衛星放送協会から今回の趣旨や衛星多チャンネル放送についてお話しし、続いてエントランスにある各国のQVCが流れるライブモニターをみながら、広報の方からQVCの会社概要について説明して頂き、その後は見学コースに沿って、会社紹介の映像や生放送スタジオを見学し、QVCについて更に知識を深めました。

続いて、コールセンターのオペレーター体験。まず、普段はオペレーターの指導を担当する方から、コールセンターの仕事、オペレーターの役割、コミュニケーションの取り方などを、楽しいクイズを交えながら解説していただきました。次に、コールセンターエリアへ移動し、実際にオペレーターのすぐそばでお客様との会話を聞きながら、どのようにお客様と接しているかを見学しました。正確に素早く、丁寧な言葉使いで対応するオペレーターに、参加者は感動した様子で一同に目を丸くしていました。
今回のテーマは、『24時間生放送の裏側を探検しよう!』ということで、撮影で使う商品サンプルが保管されている商品倉庫と、放送関係施設も見学することができました。最初に、1階の商品倉庫へ移動。背の高い棚には、7万点もの商品がきれいに整頓され、商品1つ1つには保管場所を示す『アドレス』が付いています。ここで子供たちは、宝探しゲームとして商品の『アドレス』が書かれた紙を手にして、商品を探す体験をしました。次に、QVCが生放送するための心臓部となる、ライブ・コントロール・ルームに移動し、カメラのスイッチング、テロップ情報や音声等をコントロールする部屋を見学しました。参加者は、1人で5台のスタジオカメラを遠隔で操作したり、映像を切り替えるスイッチングを体験し、初めは恐る恐る機材に触れていた子供たちでしたが、すぐに慣れて楽しそうに操作していました。

最後に、スタジオへ移動。『テレビマンチャレンジ 生放送の仕事を体感しよう!』として、「ナビゲーターチャレンジ」「ディスプレイチャレンジ」「カメラチャレンジ」を体験しました。ナビゲーターチャレンジでは、番組内で商品を紹介するナビゲーターになったつもりで、カメラが商品に寄っても手持ちした商品を動かさないように固定させる体験をしましたが、これには一同大苦戦。出演中のナビゲーターは、商品を動かさずにコメントしなければならず、皆さんの苦労を身に染みて感じることができました。ディスプレイチャレンジでは、商品を魅力的に見せるディスプレイを体験。商品を置く台や造花など、様々な小道具と背景画を駆使して、カメラの映像を確認しながらディスプレイを作成し、つい夢中になって何パターンものディスプレイを作るお子さんもいました。カメラチャレンジでは、生放送で使用しているスタジオカメラとクレーンカメラを触り、動く模型の電車を撮影する体験をしました。最近の子供たちは動画撮影に慣れているのか、動く被写体をフレームから外さず上手にとらえていました。また、本職のカメラマンに補助して頂きながら最新の4Kカメラを肩にかついで撮影する貴重な体験もありました。最後の質問コーナーでは「カメラマンになるためにはどうすれば良いですか?」など、たくさんの質問が出され、将来の仕事を考える上でまたとない体験になったようです。

衛星放送協会では、青少年が将来に向け大きな夢を持ち、職業人となる自覚を高めてもらうことを願い、青少年健全育成活動を実施しております。今後も、このような番組制作の現場体験を様々な形で継続して参ります。
| 開催日時 | 平成30年3月24日(土)12:00~17:30 |
|---|---|
| 場所 | 千葉市美浜区 QVCスクエア(QVCジャパン社屋) |
| 会場 | 世界最大級のテレビショッピング専門チャンネルQVCの社屋(QVCスクエア)で、QVC社屋設備・番組放送スタジオ・コールセンター等を親子で見学・体験。 |
| 参加者 | 新小学5年生~新中学生(保護者1名同伴) |
第22回倫理委員会・CAB-J共催セミナー
2018.03.05

山本一広専務理事
第22回となる倫理委員会・CAB-J共催セミナーが、3月1日(木)に衛星放送協会会議室にて開催されました。今回は公益社団法人日本広告審査機構(JARO)の山本一広専務理事を講師にお迎えし、「広告・表示のフェアプレイ-適正な広告・表示を実現するために-」をテーマに講演を実施していただきました。
2017年度上半期におけるJAROでの総受付件数は5,283件で、これは前年同期比104.5%。うち苦情が3,842件(同106.9%)、照会が847件(同92.3%)、広告以外が594件(同109%)となりました。件数アップの要因はオンライン受付の相談増加によるところが大きく、業種別でみるとデジタルコンテンツ等が前年同期に引き続き1位、スマホゲームや電子コミックへの苦情・ご意見が増えた影響でした。媒体別では前年同期より若干減ったものの依然としてテレビが2000件弱の第1位、昨年は1000件弱だったインターネットが1250件弱と3割アップし2位、インターネット広告への苦情・ご意見の増加が目立つ傾向とのお話でした。
総受付件数5,283件のうちJAROの審査対象となり見解が出された件数は19件で前年同期と同数ではありましたが、最も重い処分の警告が16件と3件アップし、法違反のおそれは増加傾向でした。対象媒体ではインターネット広告が14件の1位(前年同期12件)、前年4件で2位だったテレビは1件のみで3位となり減少傾向ということでした。
今年度に入り、消費者庁の措置命令件数も大幅に増えています。優良誤認を招く表現・有利誤認に繋がる不適切な二重価格表示・おとり広告といった不当表示は、広告業界の公正な発展を阻害するものです。また、医薬品医療機器等法第66条では広告主だけではなく媒体社も責任対象とされる可能性も否定できない事からも、単に広告主の問題という認識を改める必要があります。考査や広告の適正化が消費者保護に繋がり社会の健全な発展に寄与することで結果、媒体社の出稿量増加になるという、近江商人の三方よしの精神が何より大切ではないかとの講演内容でした。
| 開催日時 | 平成30年3月1日(木)14:00~15:00 |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会会議室 |
| 講師 | 公益社団法人日本広告審査機構 専務理事 山本一広氏 |
| 参加社数 | 22社 31名 |
第12回人材育成セミナー
2018.03.02
2月8日に、第12回人材育成セミナー『VRから見るコンテンツビジネス』を開催しました。
近年注目を集めるVirtual Reality (以下VR)の基礎から市場、技術の進歩や課題、放送との接点をテーマに、講師は現在VR業界の最先端で活躍される、株式会社NTTドコモ 移動機開発部第二イノベーション推進担当課長 的場直人氏、株式会社VRデザイン研究所 代表取締役所長 勝野明彦氏、株式会社積木製作 取締役マネージャー 赤崎信也氏、株式会社eje VR推進部執行役員 待場勝利氏の4名をお迎えしました。
また、会場内にVRデモスペースを設け、VRの実機に触れる「体験会」も実施して、参加者は最新のVR技術が実感できるセミナーとなりました。

(写真提供:サテマガBI)
第1部は的場氏が「VRビジネスの現状とちょっと先のVR!」というテーマで講演され、「VRの可能性」「VRビジネスの現状」「5G時代のVR」以上3つのサブテーマを軸に、スポーツ・音楽ライブ・イベントなど没入感・臨場感を高めるVRコンテンツが放送(エンターテイメント)に親和性があると思われること、市中で行われているVR実証実験(2K・4K・8K)ではエンターテイメント目的の映像配信のみではなく観光案内や医療などで利用できるか試されていること、将来的にはVRコンテンツ販売(ゲームを含む)・周辺機器販売・システム開発受託・プラットフォーム提供などビジネスへの拡がりも期待でき、近い将来の5G時代には回線の大容量化で様々な実験の中から幾つかは実用化される可能性を感じているとのお話しでした。

(写真提供:サテマガBI)
第2部のパネルディスカッションでは、モデレータに勝野氏、パネリストに赤崎氏、待場氏、的場氏にご登壇頂き、「どうなる2018年VRビジネス!と2020年までの展開ロードマップ」と題して、各社の事例を紹介頂きながら今後のVR活用の可能性についてディスカッションして頂きました。
赤崎氏からは、現在建築現場では研修用VRが活用されているが、建築に限らず3DCADデータを持つ製造業者・インフラ業者がデータをVR化し、安全対策・教育への利用が増えているとのことです。待場氏からは、パルコ屋上で行ったイギリス人の人気アーティスト「アンダーワールド」の100人ライブのVR配信が、コンシューマから好反応だったことや、横浜ベイスターズの主催試合で横浜スタジアムにVRブースをシーズン通して設置したことや、VR体験できる店舗常設型サービス「VR THEATER」が500ヶ所以上に拡がった実績が紹介されました。一方で、まだアウトプット先は狭く、何が最適なのか見えない中で、今後益々コンシューマ向けにタッチポイントの拡大が必要とのことでした。今後、5Gの通信インフラによって、リアルタイム性のあるスポーツ・音楽ライブのVR活用が想定され、他にも映像やサービスの可能性があることや、的場氏からは2020年東京オリンピックに向けた展開では、ハード・ソフトの規格化、視聴者に“楽しみ方”の周知、VRを飽きさせず見続けて頂くなどの課題が指摘されました。

また、VRと放送の接点と可能性については、今後VRコンテンツとライトユーザーを増やす視点から、米国のNextVR社の動向に注目していることが取上げられました。
| 開催日時 | 平成30年2月8日(木) |
|---|---|
| 会場 | 衛星放送協会 |
| 参加社数 | 22社 47名 |
著作権委員会セミナー「著作権実践講座」
2018.03.02
平成29年度の著作権委員会主催のセミナーは、『著作権実践講座』と題し、番組制作業務を行う上で頭を悩ませることも少なくない身近な諸問題の捉え方や対処法について、著作権委員がアドバイザーとなり解説する形式で開催しました。
本形式での開催は、平成27年度実施の『著作権基礎講座2015』に続き2回目の事となりましたが、普遍的テーマに加え「インターネットサービス拡大に伴う権利処理」といった新たなテーマの取り上げもあり、今回も様々な部門の担当者が参加され関心の高さがうかがわれました。

セミナー前半では、音楽の著作権と著作隣接権について「放送番組の二次利用」における権利処理、包括契約における「番宣動画の利用」の範囲等、又、映像作品の権利構造と二次利用する際に注意すべきポイント等について解説。セミナー後半では、具体的な“あるある事例”を多く交えて「写り込み」「一般の方の肖像の取扱い」「音楽の改変利用」等についてQ&A方式で解説しました。
参加者からも身近な具体的事案に関する質問が多く、担当ジャンルの委員から解釈のアドバイスがなされる等、良き共有の機会となりました。セミナー後のアンケートでは「具体的事例を交えての解説は分かりやすかった」「今さら聞けない基本的なことが聞けた」「他社さんの考えも聞けて参考になった」とのご意見を多く頂くことが出来ました。
| 開催日時 | 平成30年2月15日(木)13:30~16:00 |
|---|---|
| 会場 | 明治記念館 丹頂の間 |
| 講師 | 著作権委員会メンバー |
| 参加社数 | 39社 87名 |
多チャンネル放送研究所 第9回発表会まとめ
2018.01.24
多チャンネル放送研究所では毎年秋にそれまでの一年間の活動をまとめる発表会を行っていますが、今回第9回目は2017年11月28日(火)に明治記念館で開催いたしました。
発表会では研究所の3つのWGがそれぞれの研究内容を発表し、それを受けて所長の音 好宏からまとめの講義を行う形で進められました。概要は次の通りです。
■ ユーザー分析WG

清正 徹 ユーザー分析WG主査
(写真提供:サテマガBI)
2017年~2018年にかけて2年に渡り、映像がどのように利用されているか、見られているかを探る視聴実態調査を実施しており今回はその中間報告となる。
「映像の多様化」がテーマであるが、多様化にはいくつかの要因がある。PC、スマホ、タブレットといった「視聴デバイス(モニター)の多様化」、OTT系事業者による映像サービスや放送事業者による配信サービスなど「映像サービス(プラットフォーム)の多様化」、放送に加えて配信事業者もオリジナルコンテンツを制作、映画/ドラマのコンテンツホルダーが海外から参入など「コンテンツサプライヤーの多様化」など、複雑になっているのが現状である。「テレビを見なくなった」と言われているがテレビ受像機が使われなくなったのか、映像のプラットフォームのニーズが変化してきたのか、コンテンツへの接し方が変化してきたのか、それぞれについて掘り下げて調査する必要がある。
今回の調査は「ここまでの10年に映像の視聴の仕方がどのように変化してきたのか」、「この先10年はどのような視聴のされ方が主流になるのか」について、現在の映像視聴の仕方を深く分析することで今後のヒントを得ることを目的にしている。
2017年7月にインターネットを使った事前定量調査を実施し、映像視聴時間が多い/少ないといった縦軸、情報収集が積極的/消極的といった横軸でユーザーを「先進層(多様な機器を使いこなし、情報収集も積極的)」、「映像親密層(情報感度はさほど高くないものの、映像接触には貪欲)」、「情報関心層(映像の視聴量は少ないものの、情報収集は積極的)」、「低関心層(映像の視聴量が少なく、情報収集は消極的)」の4つのセグメントに分けた。先進層22%、低関心層34.5%、残りが映像親密層、情報関心層といった割合になっている。事前定量調査のデモグラフィックだけでは大きな差は出ていないが、現在利用しているサービスでは映像視聴時間が多いユーザーである「映像親密層」、「先進層」が有料放送の契約、利用率が他の層より高めとなった。一方、情報感度が高いユーザーは有料、無料のOTTの利用率が「映像親密層」、「低関心層」よりも高くなった。認知している放送サービス、配信サービスの数も、情報感度が高いユーザーが放送で4~5サービス、配信で9強ぐらいのサービス数を認知している。また、「映像親密層」、「低関心層」は、平均すると1~2サービスの認知数という結果になった。よく見るジャンルでは大差は無いが、ジャンル数では「先進層」は非常に幅広いジャンルのコンテンツを見られていた。
「先進層」の視聴実態について定点カメラや訪問インタビューを55歳男性と28歳男性の2名に行ったところ、リアルタイムではほとんど見ない「タイムシフト中心」であることや映像サービスの内容、新商品の知識は豊富にあるなどの共通点があるものの、同じ「先進層」においても年齢によって嗜好が異なること、コンテンツを所有するか利用するのか、可処分所得が低い/高いといった分け方も出来、さらに誰と一緒にコンテンツを利用しているのか、自分中心にコンテンツを見ているのか、あるいは家族で視聴することを前提に利用しているのかという分け方も出来た。このようにカテゴリー毎でもさらにいろいろな階層化が進んできており、それぞれの階層で今後仮説を立てて調査する必要がある。定性調査も2件始めたばかりであり、今後さらに多くの家庭を訪問して、最終的にまた定量調査を予定している。明らかにしていきたい課題は、映像の見方の階層化がどのように進んでいるのか、同じ「先進層」でも、こだわり、世代、お金の使い方、家族構成から異なった背景が垣間見える為、今後明らかにしていきたい。また、「先進層」の視聴行動が1マニアにすぎないのか、将来的に「映像親密層」や「情報関心層」へその見方が波及するのかを注視する必要がある。波及する場合、「先進層」の視聴行動が将来的な映像視聴の先駆けとして参考になると考えるが、波及しない場合はそれぞれのカテゴリー、それぞれの階層ごとに異なった視聴形態となっていく可能性もあり、細かく調査していく必要がある。
今後はテレビの見られ方、テレビ受像機の使われ方を調査する必要があり、テレビ受像機で放送以外のサービスがどのように利用されているのか、特に「ながら」で見るコンテンツ、集中して見るコンテンツのすみ分けがどう行われているのか、リアルタイム放送がライフスタイルの中でどのように利用されていくのかをさらに調査していきたい。
■ 将来像予測WG

三塚 洋佑 将来像予測WG主査
(写真提供:サテマガBI)
多チャンネル放送事業者の収支状況について、分布に大きな変動はないがネット収入の平均がやや増加しており、動画配信等の収入が増加傾向、費用面では前年に続き「番組制作・購入費」の割合が増加しており、オリジナル番組の制作等コンテンツ強化の傾向は変わらない。
これらを受けた収支状況としては、費用面の増加があるものの、昨年比で50.6%が増益と回答している。
加入者の傾向としては、110サービスは横ばい傾向、124/8は毎年約数万件の減少傾向、CATVは660万件前後で推移、IPTVは昨年から減少傾向の見通しで85万件前後横ばいから減少傾向であった。経営課題として、OTTサービスを始めとした配信系のさらなる普及が影響するとの見方が多く、配信PFとしても重視する傾向が如実に表れた。 配信の実施状況でみても、自社PFでは検討段階を含め約半数が実施の方向であるが、他社PFでは7割程度に上る。4Kが市場開拓につながるかという質問に対しては、2017年1月のチャンネル認定があったこともあり、普及につながるとの回答が全体的に増加した。4Kへの取組みとしては、放送事業者として参画するという事業者の割合が33%と昨年比でほぼ倍増した。
2020年時点での放送サービスの状況については、8K高画質化の普及はほとんどなく、4Kの普及、TVの大型化やスマートTVなどハード面の進化・普及とVOD、見逃し視聴など視聴形態の多様化が進む見方が多い。
OTT事業者へのヒアリング調査は3年目を迎え、その総括として、各PFとも共通して動画配信事業が拡大傾向であることやオリジナルコンテンツの重視する点は共通している一方で、コンテンツの調達はPFの特徴に合わせ色が異なる。またVODだけでなく、IPリニア配信サービスを開始する事業者も増加しており、「販売網」や「ポイント連携」、グループ内シナジー、調達手法といった点で他社と差別化を図る傾向にある。
OTT市場をどのようにみるか 映像ソフト市場動向としては、全体で約5,000億円ほどで、昨年と大きな変化はないが、そのうち有料配信は、961億から1,256億円と増加しており、セルやレンタルの割合が相対的に低下しており、今後の予測でみても動画配信市場は堅調に伸びていくと予想されている。潜在ニーズが増加するとともに供給側の数も増加傾向であり、市場競争の激化が進み、飽和状態からプレイヤーの淘汰も予想される。
チャンネル事業者としては、OTT市場は新しいマーケットではあるものの、設備投資や権利処理コストと収益性のバランスをどのようにとるかが課題であろう。
これらのことから、有料放送事業者としては「オリジナルコンテンツの制作・権利保有」「コンテンツの再発掘」による差別化、独自性がますます重要になり、動画配信市場での収益拡大のための武器となる。技術革新によるハード面の変化により視聴スタイルも多様化が予想されその環境を見極めながら対応、進化することで市場全体の拡大にもつながるであろう。
■ コンテンツ論WG

神崎 義久 コンテンツ論WG主査
(写真提供:サテマガBI)
実態調査の結果から、昨年までは、有料放送事業者はオリジナル番組の強化を進めるとともに、OTT事業者の存在感が高まるにつれ、既存プラットフォーム事業者との関係性は多様化し、OTT事業者を横目に見ながら、コンテンツの差別化および強化に乗り出すという流れが見られた。これに対し今年度の調査結果では、オリジナル番組を制作している事業者の比率は高水準を維持しながらも、それを強化しようという意向は高止まりの気配も見えている。これは、権料の高騰や字幕への対応などで全体としてコスト増となりコンテンツ開発に回す費用が厳しくなってきていること、また投下した制作費の回収方法として他局や配信事業者への番組販売以外の手段を見出すのに苦戦していること、編成の考え方として視聴率重視が進み、視聴率の取れる番組を強化する結果として、競合チャンネル間の編成が似通ってきて差別化が困難になってきていること、といった複合的な要因が重なり合って起こっていると考えられる。
4K・8Kに対する取り組みについては、ノウハウの蓄積や宣伝の強化を目的にプラットフォーム事業者との連携による制作体制を整えて取り組む積極的な事業者がある一方で、制作費や費用対効果といった課題も残っているため消極的な姿勢の事業者も見られた。
また今年度は、東京工業大学の監事で工学博士の榎並和雅先生、慶応義塾大学メディア・コミュニケーション研究所で、憲法・メディア法がご専門の鈴木秀美先生にご協力いただき、榎並先生には主に放送技術の動向、4K8Kの進展、5GやAIが放送業界に与える影響について、鈴木先生にはIPサイマル放送と放送法の改正も含めた見通しや規制緩和などについてお話をうかがった。2020年、さらにそれ以降の放送業界の大きな方向性としては、①現在の4K8Kロードマップのみならず、様々なデバイスで動画が視聴できるようになり、新技術を使って新しいスタイルで映像が見られるようになる中での発展形として、高画質化は確実に進む。②法制度上は放送と通信の垣根は存在するが、技術的には放送と変わらない、または放送を上回るサービスを、通信で提供できるようになる、とのことだった。
多チャンネル放送業界を取り巻く環境は、現状の放送波が軸ではあるもののIPリニアによるサイマル放送という形態が一般化するにつれ、利用者はデバイスを選ばず、放送や配信やチャンネルも区別せず好きなコンテンツを楽しむ、という変化が起こると考えられる。それに伴って新たなサービスの拡がりへの対応が不可避となるが、多チャンネル放送業界がこの大きくかつ急激な変化の潮流にどうやって乗っていこうとするのか。「コンテンツのプロ」であり、「視聴者のニーズに応えるエッジの効いた番組」を生み出していくことが一つの解と考えられるものの、業界全体として世の中にどのようにアピールしていくのか、早急な対応が今後ますます問われるだろう。
■ メディア激変のなかで、多チャンネルはどう生きる

音 好宏 所長
(写真提供:サテマガBI)
ユーザー分析WGではこれまでは、ある特定の世代や階層にフォーカスをあてて調査を行ってきたが、今年は、10周年を見据え大規模な調査を実施することで、今の状況を分析すべく定量的な側面に加え定性的な要素も加えて調査を行った。定性調査では特定の個人を継続的に追いかけて分析する手法を採用した。個人の多様なメディア接触を改めて整理し、そこからある特定の方向性を検出する調査手法は、試行的側面もあるが、今の混沌とした状況を考えると有用性があると考え実施した。今までとはずいぶん違うテレビの見方のフックを感じていただけたのではないかと思うので、来年続きを報告させていただく予定にしている。将来像予測WGでは例年の実態調査に加え、OTT分析3年間の総括を実施した。OTT元年と言われた2年前、OTTは敵か味方か?という議論から始まったが、それから配信業界もずいぶん進化したことを報告させていただいた。コンテンツ論WGではコンテンツという切り口とともに技術的なトレンド、制度的な問題で整理した。全体的にテーマとしては幅広い内容となっているが、それぞれの関心のあるところを深堀し活用いただければと思う。
3つのWG報告を踏まえて整理すると、メディア利用の変化という点では、人口動態の構造的変化とお金を払ってコンテンツを買うことへのシビアさが、実感の薄い景気感によって、より浮き彫りになっていると言える。以前は、「スマホは若者」、「TVはお年寄り」という図式があったが、近年の調査では、お年寄りのTV離れを示す調査結果も出ている。職場でPCを扱っていた方々が60代、70代になってきている状況の一方、若者のスマホ普及が止まり始めている。フェイクニュースに象徴されるように、信頼できる情報を求める風潮が若者間でも表れており、シビアな選択はなされているが、良いものへの価値意識も醸成されつつある。他方、無料動画の普及も強くなってきており、チャンネルの差別化も重要である。
2年前にOTTが台頭してきたことで、コンテンツ調達面に大きな影響があるのではないかという話があったが、問題の本質は「OTTの台頭」のみではないのではないか?ということ。たとえば、競合チャンネルは、視聴率獲得のために似たような編成になることで購入競争が激化しているということをコンテンツ論WGから報告させていただいた。昨年出版の『メディア融合時代到来!』にて、多チャンネルの持っている価値の一つが多チャンネルが多様な社会を提示する、豊かな社会を提示することとまとめさせていただいたが、チャンネルがマーケットと向き合う中で、同質化、類似化という力も受けつつあるのではないかという問題提起をさせていただいた。それだけでなく4Kの本格的なスタートが多チャンネルにとってひとつの起爆剤になる可能性や、5Gといった技術動向が戦略的にどのような形で多チャンネルに有用性があるのか、制度面を追い風にできるかなども多チャンネル放送の環境変化に対応する上で重要な視点である。
昨年も少し触れたテーマでもあるが、多チャンネル放送は転換期を迎えている。OTT市場は厳しい環境下でサービスが行われており、多チャンネルもここ数年厳しい数字が並んでいる。多チャンネルの抜本的な改革が必要で、4Kをはじめとする技術の発展や各種制度をうまく追い風にし、オリジナルで魅力あるコンテンツを提示していくことで、プラスサムのマーケットをいかにデザインできるのかということが問われている。
最後にコンテンツについて触れると、日本のコンテンツは地上波の縛りによって流通ルートはかねてから硬直的であったが、20数年前に立ちあがった衛星・CATVにより多チャンネルのルートが形成され、「じもテレ」のような新しいルートの開拓もされている。今日の報告でも何度かでてきたAbemaTVは、インターネット上で展開しているが実はマスTVを狙っているのではないかという考え方にたつと、多チャンネルのもっているマス性とは何かということをもう一度考え、オリジナルアワードの中でも新しい可能性を感じるコンテンツを武器に、チャンネルルートの在り方を検討することが大切であろう。もちろんそれには多チャンネルを支える“人”であったり、今のマーケットをどう広げていくかを、ともに考えることが必要ではないか。
| 開催日時 | 平成29年11月28日(火)13:00~16:30 |
|---|---|
| 会場 | 明治記念館(港区元赤坂) |
| 参加社数 | 50社 94名 |
衛星放送協会について
- 衛星放送に関するプラットフォーム
業務に係るガイドラインに基づく委員会 - 普及促進委員会
- 衛星放送のプラットフォーム
ガイドラインに関する委員会